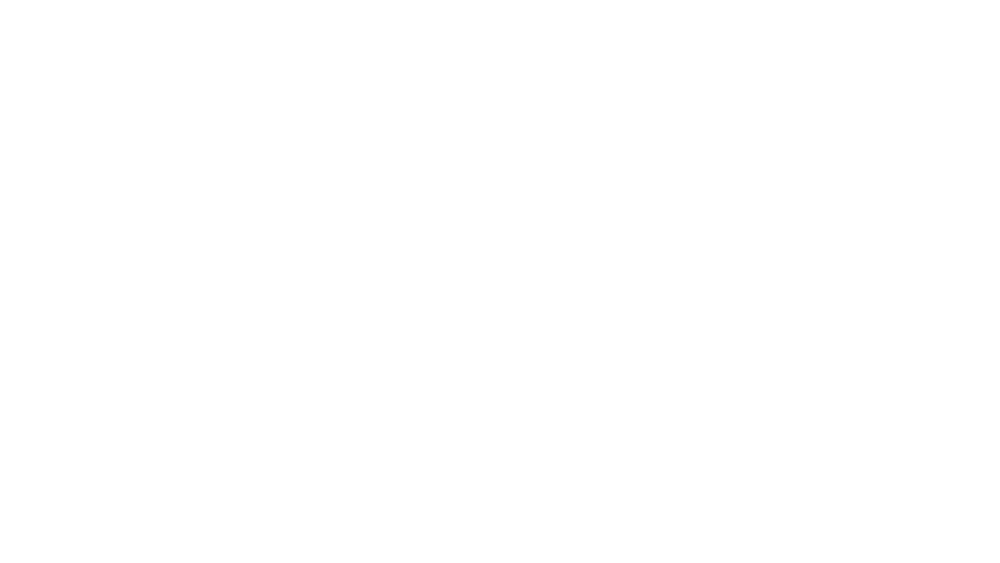写真提供先:那覇市立壷屋焼物博物館
マカイ
| 名称かな | まかい |
|---|---|
| 大分類 | 4章 おたのしみとおもてなし |
| 中分類 | 食器(食べる) |
| 解説 | ご飯や汁物を入れた碗のこと。 17世紀~18世紀のマカイは高台(本体下部の台座部分)や内側の底部付近には秞薬(ゆうやく)を施さないで、上部半分ほど(口縁部〜胴部)のみに灰釉(かいゆう)を掛けています。これは重ねて焼成されるときに釉薬によってヒッツキ(溶着)が生じるのを防ぐためです。19世紀頃からは全体に釉薬を施すようになります。これは重ね焼きの際にヒッツキが生じないように、高台の底面(畳付)には耐火度が高い粘土(メーガニク)を塗り、内側の底部の(上に重ねるマカイの高台が当たる)部分の釉薬を剥ぐ「蛇の目釉剝ぎ」技法が確立したためです。 17〜18世紀のマカイには黒い釉薬による鉄絵が施されることがあり、19世紀以降の全体的に秞薬が施されたマカイには赤絵(多彩な色合いの施釉の絵付け)のものも作られるようになりました。蛇の目釉剥ぎは南方系の技法といわれ、またトンボ文などと呼ばれる鉄絵の抽象的な文様や碗の形状も中国南部の民窯の影響を受けているとみられます。 |