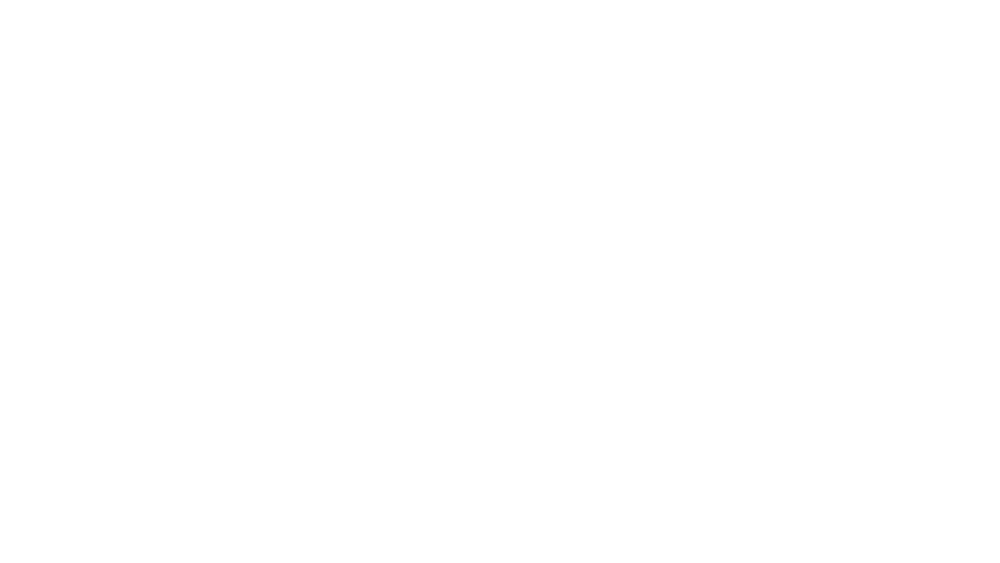「食べてきたもの」
| 解説 | 執筆:上里隆史(琉球歴史家、内閣府地域活性化伝道師) 太古より、沖縄の人々は亜熱帯と海に囲まれた自然環境の食材を食していました。サンゴ礁の内海(沖縄ではイノーという)を中心とした生活を営んできた先史時代にはイラブチャーやタマン、シャコガイやチョウセンサザエなど内海に生息する魚介類を食べていたようで、遺跡から多く出土します。マグロやカツオなどの外洋の魚の骨はほとんどなく、「海人」にイメージされるような遠洋漁業ではなく、干潟やイノーを中心とした漁労採集の生活だったことが想像されます。またイノシシやドングリなど陸上の動植物も遺跡から確認されています。海から食材を調達するライフスタイルは12世紀頃の農耕の開始で廃れたわけではなく、農耕とともに基本的には近代まで各地で続いていきました。 1372年の明との朝貢関係の開始とアジアとの中継貿易の活発化で、島の外から多くのヒトやモノが集まってきました。これにともない島外からさまざまな食材と調味料がもたらされました。15~16世紀、東南アジアから胡椒や丁子(クローブ)などの香辛料が大量にもたらされましたが、なぜか琉球で根付くことはありませんでした。この点、朝鮮王朝が胡椒の国産化に注力した動きとは対照的です。中国あるいは日本からは素麺などの麺類が入ったとみられます。15世紀の沖縄島には牛・豚・鶏肉を食べ、また馬肉や昆虫も市場に並び、酢や味噌、醤油や魚の塩辛もあった(『朝鮮王朝実録』)。 17世紀以降に沖縄にもたらされた食材のうち、サツマイモは中国福建省より野国総官が持ち帰って儀間真常が栽培に成功、以降は沖縄の日常食材として定着しました。サツマイモは豚の餌としても使われ、豚肉食の普及にも一役買いました。幕藩制国家に編入された近世琉球では蝦夷地から日本海経由で大量の昆布が流入し、大半は中国(清)に輸出されたものの、国内で食材として一般化することになりました。あわせて七島産の鰹節が薩摩より伝来、現在の琉球料理の構成要素がほぼ揃うことになりました。 この時代、国内で消費するための食材ではなく、国外輸出用の換金作物が作られるようになったのも特徴です。サトウキビは17世紀に儀間真常が生産システムと圧搾機を中国より導入し、生産された黒糖は琉球から江戸時代の日本へと渡り、大きな利益をあげました。またウコン(ウッチン。ターメリック)も琉球で栽培され、漢方薬の原料として薩摩藩経由で大坂市場にもたらされました。黒糖・ウコンの生産が近世琉球の基幹産業に成長し、その流れが現在のサトウキビ畑の風景と黒糖、お酒の供ウッチンにつながっていったのです。 |
|---|