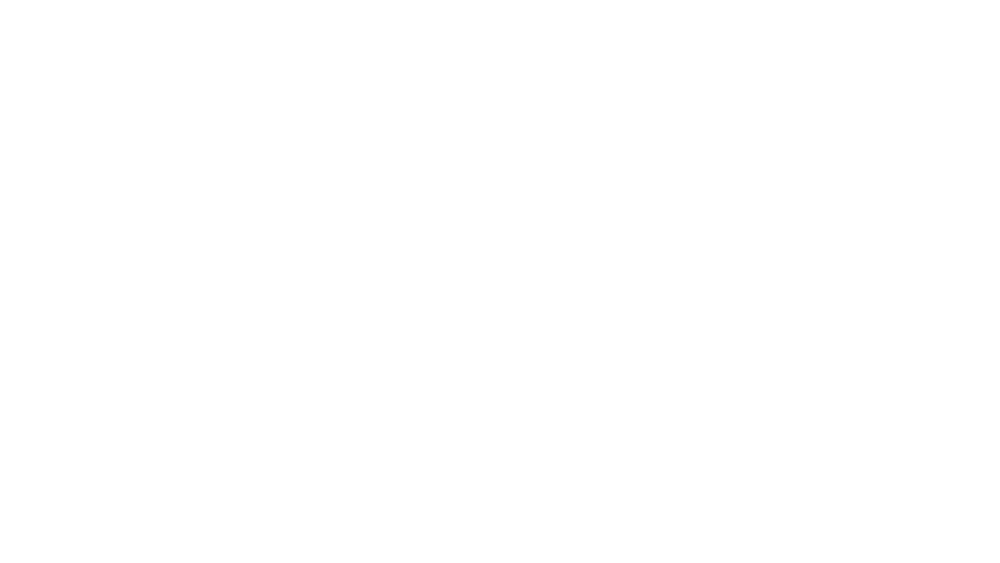飴釉緑釉流アンダガーミ
写真提供先:那覇市立壷屋焼物博物館
壺
| 名称かな | つぼ・ツボ |
|---|---|
| 大分類 | 4章 おたのしみとおもてなし |
| 中分類 | 食器(貯める) |
| 解説 | 壺と甕の区別は元々明確にはありませんが、一般にはより大型の貯蔵陶器が甕、小型の貯蔵陶器が壺と呼ばれます。油味噌の貯蔵のための高さ30cmほどの容器は一般にアンダガーミ(油甕)と呼ばれますが、ミミチブ(耳壺)とも呼ばれます。 壺も、甕と同様に、装飾のための釉薬を施さない焼締陶器が主です。先ほどのアンダガーミのように黒釉または飴釉を施す場合もありますが、装飾というより機能性のためとみられます。高さ20cmほどの頸部のある壺は、塩壺、種壺などと呼ばれます。高さ20~30cmほどの陶製の蓋を持つ壺や、同様の大きさで頸部に施釉にない壺は茶壺として使われたようです。 用途により形状が異なるともいわれますが、実際には多目的に使用された壺が多かったと考えられます。 |