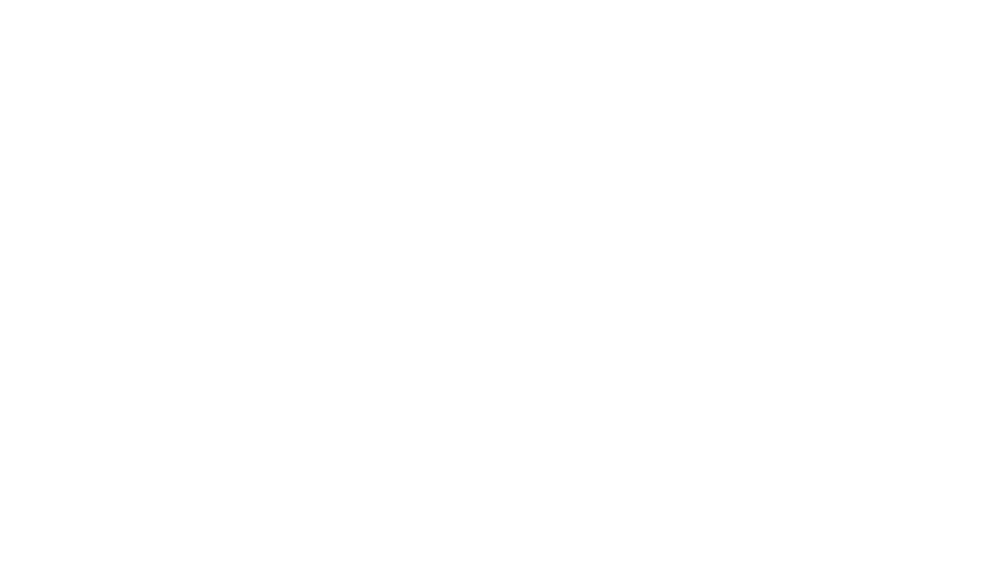/2
駿州薩陀山富士遠望図
| 作品名よみ | すんしゅうさったさんふじえんぼうず |
|---|---|
| 作品名(欧文) | Distant View of Mt.Fuji from Satta Pass in Suruga Province |
| 作者 | 司馬江漢 |
| 種別 | 日本画 |
| 受入番号 | 497 |
| 枝番号 | 0 |
| 分類番号 | J-093 |
| 員数 | 1面 |
| 形状 | 額装 |
| 寸法(cm) | 78.5×146.5 |
| 材質 | 絹本油彩 |
| 材質英文 | Oil on silk, framed |
| 制作年(西暦) | 1804 |
| 制作年(和暦) | 文化1 |
| 記銘、年紀 | (右上)「駿州薩陀山 東都江漢 司馬峻描寫」「erste Zonders in Japan Si:」 |
| 受入年度(西暦) | 1982 |
| 受入年度(和暦) | S57 |
| 受入方法 | 購入 |
| キーワード | 風景、富士山 |
| 解説 | 司馬江漢が描いた富士山図のなかでも人気を博した、薩埵峠富士眺望図の一例である。 江漢は天明八(一七八八)年、長崎遊学の際に東海道を旅し、その途上で、駿河国の久能寺(現在の鉄舟寺)から眺望した富士山のスケッチを制作した。江漢はその経験を活かし、油彩や水墨によって、さまざまな構図、表現による富士山図を描いた。 薩埵峠(静岡県清水市興津)から駿河湾越しの富士山を遠望した姿を描く本作と同図様の作品は、寛政元(一七八九)年から文化元(一八〇四)年まで、十点を超える作例が報告されており、江漢は同図様を繰り返し描いたことが知られている。 本作の景観描写は、天明八年のスケッチに基づくものと考えられるが、江漢は、実際には薩埵峠から富士山を見ることができず、矢部からの眺望を基に本作を描いた可能性が指摘されている。 本作は、江漢が描いた《富嶽図》(個人蔵)とほぼ同図様であり、一八〇〇年頃に江漢が集中的に描いた作例のなかで、最も遅く描かれた作品と考えられている。 本作と「富嶽図」を比較すると、本作には、画面左前景に松樹や家屋が描き加えられており、波濤が荒く、海岸の稜線の湾曲が強調されている。また、富士山の位置が画面中央付近に変更されており、富士山に至る海岸線の距離が長い。富士山以外の山岳の彩色にはグラデーションが用いられており、緑を多用した《富嶽図》よりも、富士山周辺の景観は、自然な色合いによって表されている。絵具を薄く掃いた白雲は透明感があり、澄んだ空気を連想させる。海面に施された水色は、画面遠景では白く輝き、透き通るように明度が高い。本作の空や海の表現には、光や大気を描き出す江漢の鋭敏な感覚がうかがわれる。 本作の規格や、山形県内に伝来したことから、本作は、文化元(一八〇四)年のものと考えられる、出羽庄内藩士・塙伊助宛の司馬江漢の書簡にある、伊助が注文した「サツタの図」であると推定されている。制作年代だけでなく、本作の表現、完成度を勘案すると、本作は、江漢の油彩による富士山図の到達点を示す作品と言えよう。 ※中野好夫『司馬江漢考』(新潮社 一九八六年) 日比野秀男「司馬江漢筆『駿州薩陀山富士遠望図』―江漢における実景と絵画化―」 (『静岡県立美術館研究紀要』四号 一九八六年) 成瀬不二雄 作品解説『司馬江漢 生涯と画業 本文篇・作品篇』 (八坂書房 一九九五年) 山下善也 作品解説『描かれた日本の風景 近世画家たちのまなざし』 (静岡県立美術館 一九九五年) 金子信久 作品解説『司馬江漢の絵画―西洋との接触、葛藤と確信』 (府中市美術館 二〇〇一年) 成瀬不二雄『富士山の絵画史』(中央公論美術出版 二〇〇五年) 福士雄也 作品解説『富士山の絵画展』(静岡県立美術館 二〇一三年) 2019年『対立と融和―十九世紀の江戸画壇』リーフレット、p. 45 |