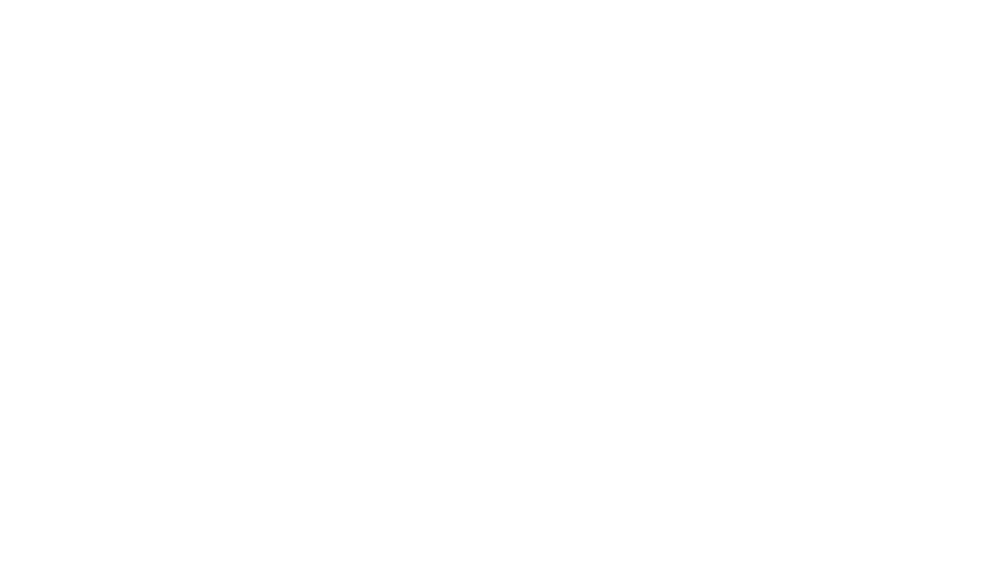右隻
/9
武蔵野図屏風
| 作品名よみ | むさしのずびょうぶ |
|---|---|
| 作品名(欧文) | Musashi-no Landscape |
| 作者 | 作者不詳 |
| 種別 | 日本画 |
| 受入番号 | 1397 |
| 枝番号 | 0 |
| 分類番号 | J-330 |
| 員数 | 6曲1双 |
| 形状 | 屏風装 |
| 寸法(cm) | (右隻)155.6×356.8(左隻)155.6×354.8 |
| 材質 | 紙本金地着色 |
| 材質英文 | Color on gold-leafed paper, a pair of six-fold screens |
| 制作年(西暦) | 17世紀 |
| 制作年(和暦) | 江戸時代前期 |
| 記銘、年紀 | (右隻左下)朱文方印(判読不能) |
| 受入年度(西暦) | 2009 |
| 受入年度(和暦) | H21 |
| 受入方法 | 購入 |
| キーワード | 名所絵、風景 |
| 解説 | 武蔵野図と呼ばれる図様は屏風絵だけを取り上げても一様ではないが、富士山と金雲、月と秋草のみで構成される本作の図様は、武蔵野図屏風のひとつの典型を示す。実景というものへの意識が希薄で、「武蔵野」が喚起する情感のみに寄り添うような画面は、この名所絵的な主題の成立が和歌に基づく文学的伝統に先導されてきたことを示していよう。 画面は大きく上下に分けられる。上半は金雲も含めて金箔で埋め尽くされ、左隻第二扇から四扇にまたがる富士山だけが浮かびあがる。退色が激しいが、富士の山肌には群青や緑青の跡が見受けられ、当初はもっと色鮮やかで存在感もあったことだろう。下半は細く均一な緑青の線で草原が表され、その中に菊や萩、桔梗といった秋の草花が咲く。画面下端の地面は緑青が埋め、その緑青部分に少し接するようにして、右隻第四扇の叢に満月が隠れる。規則的なパターンで整えられ果てしなく連続していくような図様 は、受け継がれてきた武蔵野の茫漠とした風情を思い起こさせる。 ただし、もともと和歌に詠み込まれた武蔵野のイメージには富士山は含まれておらず、一連の武蔵野図屏風に描かれる富士山は、和歌の本来の意図からははみ出すものといえる。富士山が取り込まれた理由は定かでないが、武蔵野という名所を説明するものとして、東国の象徴である富士山が描き込まれたものかもしれない。武蔵野と秋草と富士山の組合せはやがて定着し、江戸時代を通じて屏風に限らず様々に取り上げられるようになり、富士山が喚起するひとつの重要なイメージを形作った。 安達啓子「日月図屏風と武蔵野図屏風-金剛寺本日月山水図屏風を中心に-」 『日本屏風絵集成 第九巻 景物画-四季景物』講談社 一九七七年 仲町啓子「武蔵野図の系譜」 『花鳥画の世界 第五巻 瀟洒な装飾美-江戸初期の花鳥』学習研究社 一九八一年 2015年『特別展 富士山 ―信仰と芸術―』、p. 187 |