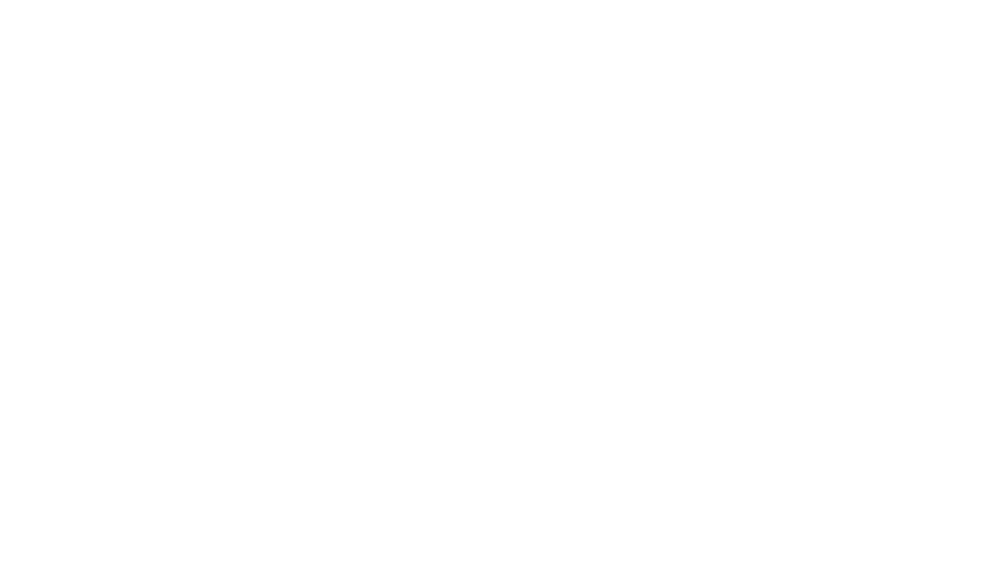風間 完 画
小林多喜二の死
| よみがな | コバヤシタキジノシ |
|---|---|
| 解説 | 昭和8(1933)年2月、東京の築地警察署で特高警察の拷問によって非業の死を遂げた小林多喜二の作品は、現在でも不滅の輝きを放っている。プロレタリア文学運動の生んだ作品で、今日も読むに耐え得るものが暁天の星ほどしかないところを見ると、多喜二にそれだけのものを書かせたのは、単なる文学理論だけではないだろう。その天性の才能を引き出し、天啓を与え育てた詩の女神(ミューズ)がいたはずである。 小樽高等商業学校を大正13(1924)年春に卒業した多喜二は、地元の北海道拓殖銀行に就職し、小樽支店に勤務した。この年の秋、多喜二はひとりの女性に出会った。銘酒屋の酌婦、田口たきである。たきの父親は屋台そばを売り歩きながら、たくさんの家族を養っていたが、たきが十五歳のときに商売に失敗して夜逃げし、たきは銘酒屋に売られた。銘酒屋とは、飲み屋を装った売春宿である。父親は間もなく鉄道自殺を遂げた。 たきは心根やさしく、生きる姿勢はけなげであった。多喜二に望まれて何度か同棲しつつ、飲んだくれの日雇い労働者と再婚した母や家族たちを助け、文学を理解しようと啄木の短歌を読んだ。 自分のような者が一緒にいては、創作活動にも銀行勤務にも支障があるだろうと置き手紙をして、身を引いてもいる。多喜二がたきを追ったのは、恋していたからであり、彼女の存在が旺盛な創作活動の源泉だったからだろう。多喜二は真剣に求婚したが、たきは彼に迷惑のかかることを恐れて、承諾を与えなかった。 正式の夫婦にこそならなかったが、三十歳の途半ばで多喜二が世を去るまで、彼女は多喜二のミューズでありつづけた。そういう人生だったのだ。 (「昭和史発掘」?) |
| 作品名 | 昭和史発掘 |