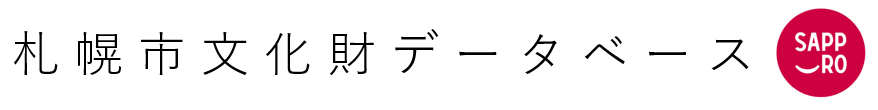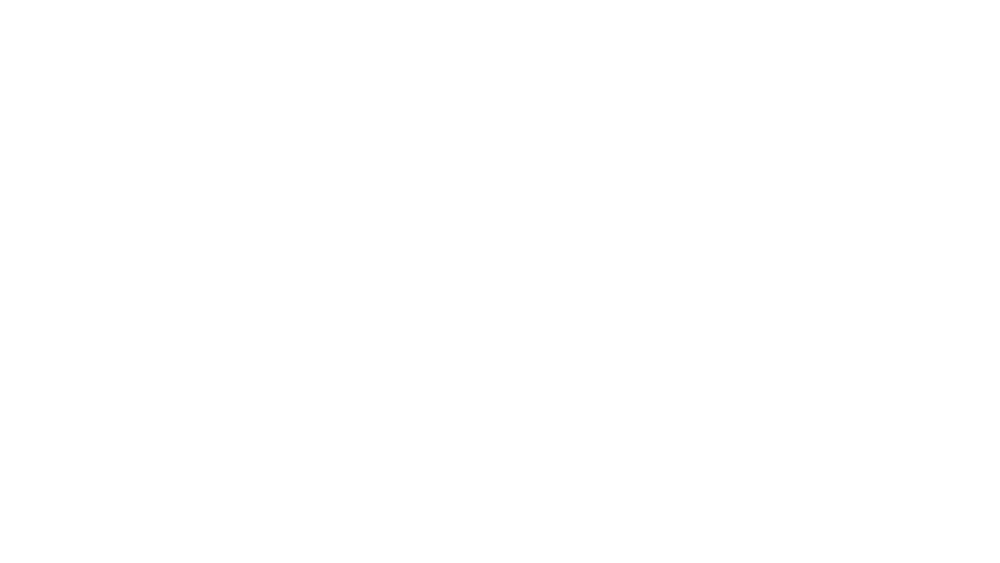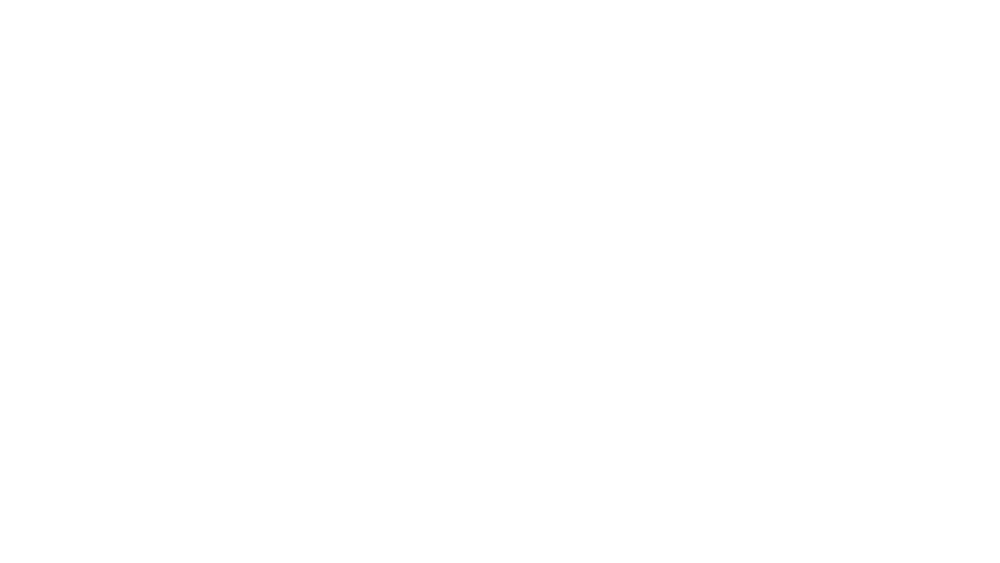北海道大学理学部本館・ 総合博物館
| 分類 | 歴史的建造物 |
|---|---|
| 資料番号 | 56 |
| 所在/住所 | 札幌市北区北10条西8丁目(北大構内) |
| 竣工年 | 1929(昭和4)年 |
| 構造及び形式 | RC造 3階建 |
| 解説 | 北海道帝国大学となった翌年(1920/大正9年)、農学部と医学部が設置され、さらに総合大学を目指して理学部と法文学部等の新設運動が展開されたが、先に工学部(1924年)が開設され、理学部は関東大震災後の1926(大正15)年11月に設置費が閣議決定された。同年9月18日の北海道帝国大学新聞に「理学部講堂」として、設計概要と完成予想透視図が紹介されている。 1927(昭和2)年11月に基礎工事が着手され、1929年11月に竣工。翌年、付属建物も落成し、4月に理学部が開学。起工から丸2年を要して完成した3階建ての本館は、正面91m×側面78mのコの字型プランで延床面積が1万平方メートルを超える、当時札幌市でも数少ない大規模な鉄筋コンクリート造建築である。 本館正面の東棟内側には4階建ての書庫・閲覧室が設置され、南棟奥に温室が併設された。 設計者の萩原惇正が意図した「今迄の講堂とは全然趣きの変つた味のある建築」は、当時「超モダーンな偉容」(北海タイムス 1930.4.1)として注目されたが、その外観や内部意匠には10世紀末以降の西欧キリスト教建築で生み出された2つの様式が折衷されている。スクラッチタイルを用いた外観には、軒下の小アーチ列(ロンバルト帯)や窓上部の半円アーチ、外壁の構造補強の柱型壁(バットレス)などロマネスク様式の要素が見られ、正面玄関前の車寄せの尖りアーチや中央階段室の吹き抜け上部のリブヴォールトなどゴシック様式の意匠が加味されている。 F.L.ライト設計の帝国ホテル(1923年)から始まり、昭和初期に流行ったと言われる スクラッチタイル壁は、あえて混色のタイルが採用され、陰影のある外観を見せている。 階段室上部の壁面四方に、「果物」「ひまわり」「コウモリ」「ミミズク」の円盤形陶製レリーフが1枚ずつ飾られている。それぞれ朝、昼、夕方、夜を意味し、昼夜の別なく学問研究に励めという想いが込められており、設計者の萩原課長の創案によりフランス人職人が製作したという。 階段室上部に見られるリブヴォールトの空間は「アインシュタイ・ドーム」と愛称されて、この建物一番の見所となっている。 |
| 調査日 | 2010年 |
・キーワード検索のカナ、記号、英数は、全角・半角を区別して入力ください 。 ・本サイトで紹介する建造物等は、一般に公開されているものを除き、内部の観覧や敷地への立ち入りは出来ません。 ・郷土資料館収蔵品を閲覧希望する場合、事前に名称等を郷土資料館までお伝えいただいた上で、ご来館いただけると、 お待たせする時間が少なくなります。 各郷土資料館の連絡先はこちらです。 |
【問い合わせ先】札幌市市民文化局文化部文化財課 〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目札幌時計台ビル10階 TEL:011-211-2312 FAX:011-218-5157
【ご利用上の注意】本データベースのテキスト・画像の無断での転用・転載・加工等の行為を固く禁じます。