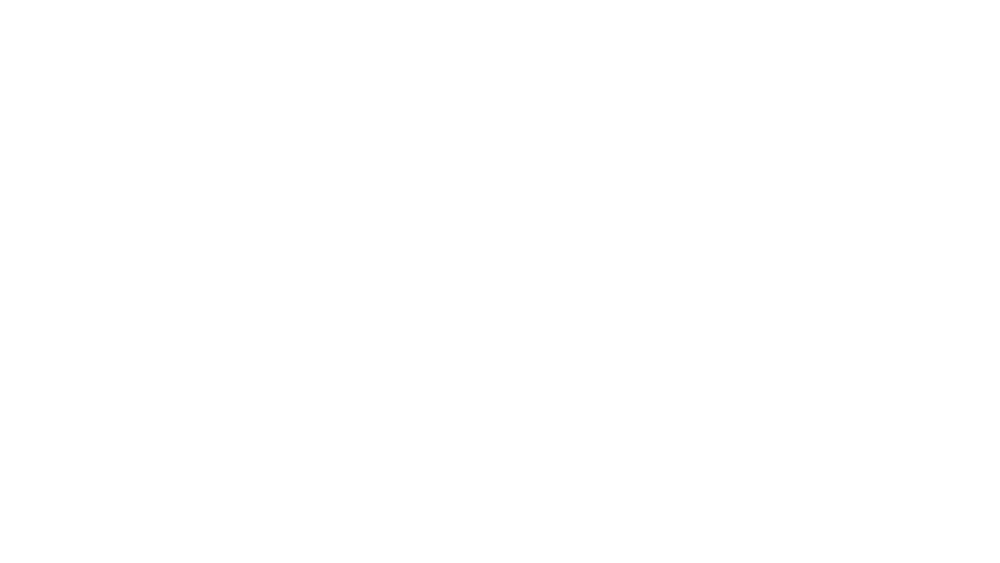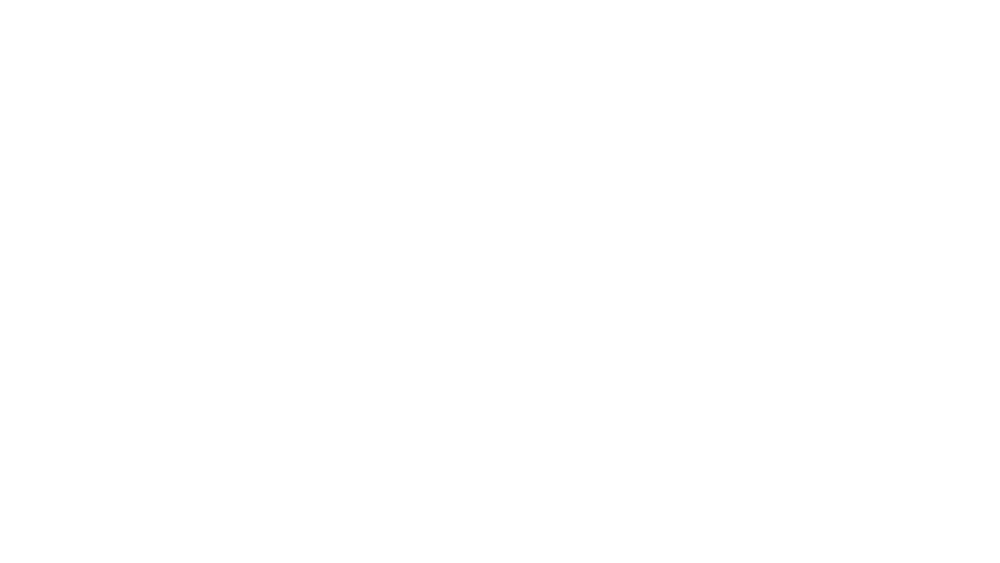肥桶
| 時代(公開用) | 昭和30年頃まで |
|---|---|
| 寸法(公開用:民俗) | 高さ575×幅φ375㎜ |
| 材質 | 木 |
| 資料解説 | 人の大便や小便は肥料となったので、便所(トイレ)にたまったものを、この桶に入れて田畑に近くの「肥だめ」という保存場所に運び、腐熟させてから肥料として使った。焼印から江戸川区の桶屋で作られたことがわかる。(「東京都江戸川区南篠﨑207桶由製作所」の焼印あり) 昭和のはじめごろには化学肥料が取り入れられるようになったが戦中・戦後は入手困難となり、下肥が多く使われた。国立の農家は、立川や杉並あたりからも人糞尿を運んだ人もいた。そのころは人糞尿をもらうと、農家はもらった家にお礼に野菜などを渡した。1955(昭和30)年ごろまでは、家庭から出た人糞尿(大便・小便)は、肥料として農家で利用されていた。しかし、この頃から農家以外の人口増加に対し農地は逆に減ってきたことや、化学肥料が安く手に入るようになり農家が下肥を使わなくなったことで、人糞尿の回収が追いつかず、全国的に大きな課題となっていった。国立では、この問題の解決のため1958(昭和33)年には化学処理方式の”し尿処理施設”「清化園」の設置がきまり、1961(昭和36)年に竣功した。 桶の釣り手部分を除く高さ450㎜ フタの把手の長さ①長い方425㎜②短い方355㎜ 付属の縄の全長229㎜ 参考:『国立の生活誌Ⅵ』P239に「下肥運び」の記載あり |
| 資料番号 | M02672 |
くにたち郷土文化館が収蔵する資料の一部を公開しています。
本データベースで公開されている画像の無断利用を禁じます。
当館が所蔵する資料および画像の利用を希望する場合は、当館ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。
本データベースで公開されている画像の無断利用を禁じます。
当館が所蔵する資料および画像の利用を希望する場合は、当館ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。
======================================================
・2025年11月6日 国立市広報移管写真の新規公開を開始しました(2026年2月18日現在:158点公開中)。
・2025年3月25日 民具資料21点を追加しました。
・2024年3月28日 民具資料21点を追加しました。
・2023年3月20日 甲野勇氏資料26点を追加しました。追加資料の一覧はこちら(PDF)。
・2025年3月25日 民具資料21点を追加しました。
・2024年3月28日 民具資料21点を追加しました。
・2023年3月20日 甲野勇氏資料26点を追加しました。追加資料の一覧はこちら(PDF)。
◆検索方法◆
- キーワード:入力式。「全ての語を含む」、「いずれかの語を含む」のいずれかを選択することが出来ます。
- 分 類:プルダウン式。検索したいジャンルを選んで「検索」のボタンを押します。現在「歴史」「民俗」「写真」のみ。
- 資 料 名:入力式。部分一致検索を行います。
- 資 料 群 名:プルダウン式。資料群の詳細については、下記の「◆掲載資料◆」をご覧下さい。
- 形 態:チェックボックス式。複数選択可。
- 年代(西暦):入力式。部分一致検索を行います。※時代(和暦)のみで登録されている資料は検出されません。
- 時代(和暦):プルダウン式。検索したい元号を選択して下さい。
◆掲載資料◆
- 甲野勇氏資料:縄文土器の編年で著名な考古学者 甲野勇(1901-1967)氏旧蔵の資料群。書籍、雑誌、写真、実測図、拓本、論文・講義の原稿等、約8,600件。甲野氏は、1946年から1967年に亡くなるまでの約20年間を国立に暮らし、多摩地域の郷土史研究や、小・中・高校生への発掘指導などの社会教育事業を積極的に行ったことでも有名です。
- 民俗資料:くにたち郷土文化館に収蔵されている、地域の生活をあらわす資料。
- 国立市広報移管写真:国立市広報が広報誌等への掲載のために撮影した写真で、昭和30年代から2002年度までの35㎜ネガフィルム等が、くにたち郷土文化館に移管されています。地域を知る上で貴重な写真が数多く含まれており、くにたち郷土文化館でデジタル化を進めている資料群です。
◆データベースの利用にあたって◆
- 本データベースで公開されている画像の無断利用を禁じます。
- 当館が所蔵する資料および画像の利用を希望する場合は、当館ホームページの「お問い合わせ」よりご連絡ください。
- 利用希望の連絡を受け取ってから許可書を発行するまでに、早くとも1週間程度の時間を要します。余裕をもってご申請ください。
- 本データベースは利用者への予告なく内容の変更等をする場合があります。
- 当館は、本データベース利用者の行為について、何ら責任を負うものではありません。