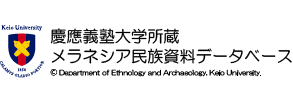慶應義塾大学 文学部民族学考古学研究室
はじめに
慶應義塾大学には、メラネシアの島々で収集された民族資料が1800点余り収蔵される。主たる資料は、戦前・戦中に南洋群島で製糖業を展開していた南洋興発株式会社社長、松江春次氏のコレクションであった。そのなかには、明治期から独領ニューギニアで貿易業を営んでいた小嶺磯吉氏の収集品も多数含まれている。慶應義塾大学の民族学研究を主導した松本信廣先生が中心となり、コレクションの図録が昭和15年に刊行されている。松江氏のご子息が塾生だった縁もあり、終戦直後に三田キャンパスで所蔵されることとなった。世界的にも貴重な民族資料群である。
■ 参考文献
・山口 徹 2015 「ウリ像をめぐる絡み合いの歴史人類学:ビスマルク群島ニューアイルランド島の造形物に関する予察」『史学』85(1-3): 401-439
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20150700-0401
・臺 浩亮 2020 「植民地期のニューギニアにおける小嶺磯吉の活動に関する予察:一九〇五年から一九一一年における収集活動を中心に」『史学』89(3): 1-52
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20201200-0001
1. 「推定収集地」について
・小嶺磯吉ならびに南洋興発株式会社によって収集された民族資料については『ニウギニア⼟俗品圖集』や民族学考古学研究室が管理する資料カードに記載される情報、整理作業・類例検索の過程で得られた情報、シカゴ・フィールド博物館に所蔵される小嶺磯吉の収集品の情報を総合的に判断し、より可能性が高い地域を記載した。
・西北ソロモン調査団ならびにレンネル島調査団によって収集された民族資料については民族学考古学研究室が管理する資料カードに記載される情報を記載した。
2.掲載写真について
モノクロ写真は1970年代に在籍していた民族学考古学研究室所属の学生によって撮影されたもの、またカラー写真は2013年以降に民族学考古学研究室所属の教員・学生によって撮影されたものである。
3.解説文について
2015年以降に開催された民族学考古学研究室主催の展覧会にて掲載された解説文ならびに有志が執筆した解説文を本データベース上にて掲載している。未掲載の資料解説についても順次公開する予定である。
4.メラネシア民族資料整理およびデータベース編集参加者について
メラネシア民族資料データベース編集ならびに資料整理作業参加者は以下の通り(敬称略)
<データベース編集者>
山口徹(慶大・文・教授)、臺浩亮(慶大・文研・後期博士課程)、太刀川彩子(慶大・文研・修士課程)
<資料整理作業参加者>
安藤香里、市田直一郎、岩浪雛子、嘉生泰花、川本智仁、木下圭祐、黑川由紀⼦、⼩林真⾐⼦、⼩林⻯太、佐山のの、下⽥健太郎、鈴木伸太朗、鈴木帆奈、臺浩亮、太刀川彩子、田中祐壮、遠山裕佳里、長尾琢磨、長澤良佳、成澤可奈子、藤田絢花、牧田侑子、町田竜太郎、村井南、吉⽥友⾥恵
5.その他
本データベースに掲載されるメラネシア民族資料は民族学考古学研究室が管理しています。研究室の活動や資料に関するお問い合わせについては研究室ホームページ(http://web.flet.keio.ac.jp/~toru38/ethnoarch/)をご参照ください。
なお、所蔵資料の基礎情報に関する調査に際して、以下の研究助成事業にご支援いただきました。
・「植民地期に収集されたオセアニア造形物に収集側と譲渡側の交錯を読み解く歴史人類学」(代表者:臺浩亮、2017年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(研究科推薦枠)、2017年4月1日~2018年3月31日)
・「20世紀初頭収集のメラネシア造形物に日本人収集者の戦略と交渉を読み解く歴史人類学」(代表者:臺浩亮、2018年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(全塾選抜枠)2018年4月1日~2019年3月31日)
・「20世紀初頭のメラネシアを巡るコレクティング・コロニアリズム研究:モノから『収集の民族誌』を描く」(代表者:臺浩亮、公益信託澁澤民族学振興基金 平成30年度 大学院生等に対する研究活動助成、2018年4月1日~2019年3月31日)
・「植民地期のニューギニアにおける『収集の現場』とモノを巡る戦略・交渉の博物館人類学」(代表者:臺浩亮、2019年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(研究科推薦枠)、2019年4月1日~2020年3月31日)
(最終更新日 2022.1.2)
慶應義塾大学には、メラネシアの島々で収集された民族資料が1800点余り収蔵される。主たる資料は、戦前・戦中に南洋群島で製糖業を展開していた南洋興発株式会社社長、松江春次氏のコレクションであった。そのなかには、明治期から独領ニューギニアで貿易業を営んでいた小嶺磯吉氏の収集品も多数含まれている。慶應義塾大学の民族学研究を主導した松本信廣先生が中心となり、コレクションの図録が昭和15年に刊行されている。松江氏のご子息が塾生だった縁もあり、終戦直後に三田キャンパスで所蔵されることとなった。世界的にも貴重な民族資料群である。
■ 参考文献
・山口 徹 2015 「ウリ像をめぐる絡み合いの歴史人類学:ビスマルク群島ニューアイルランド島の造形物に関する予察」『史学』85(1-3): 401-439
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20150700-0401
・臺 浩亮 2020 「植民地期のニューギニアにおける小嶺磯吉の活動に関する予察:一九〇五年から一九一一年における収集活動を中心に」『史学』89(3): 1-52
https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20201200-0001
1. 「推定収集地」について
・小嶺磯吉ならびに南洋興発株式会社によって収集された民族資料については『ニウギニア⼟俗品圖集』や民族学考古学研究室が管理する資料カードに記載される情報、整理作業・類例検索の過程で得られた情報、シカゴ・フィールド博物館に所蔵される小嶺磯吉の収集品の情報を総合的に判断し、より可能性が高い地域を記載した。
・西北ソロモン調査団ならびにレンネル島調査団によって収集された民族資料については民族学考古学研究室が管理する資料カードに記載される情報を記載した。
2.掲載写真について
モノクロ写真は1970年代に在籍していた民族学考古学研究室所属の学生によって撮影されたもの、またカラー写真は2013年以降に民族学考古学研究室所属の教員・学生によって撮影されたものである。
3.解説文について
2015年以降に開催された民族学考古学研究室主催の展覧会にて掲載された解説文ならびに有志が執筆した解説文を本データベース上にて掲載している。未掲載の資料解説についても順次公開する予定である。
4.メラネシア民族資料整理およびデータベース編集参加者について
メラネシア民族資料データベース編集ならびに資料整理作業参加者は以下の通り(敬称略)
<データベース編集者>
山口徹(慶大・文・教授)、臺浩亮(慶大・文研・後期博士課程)、太刀川彩子(慶大・文研・修士課程)
<資料整理作業参加者>
安藤香里、市田直一郎、岩浪雛子、嘉生泰花、川本智仁、木下圭祐、黑川由紀⼦、⼩林真⾐⼦、⼩林⻯太、佐山のの、下⽥健太郎、鈴木伸太朗、鈴木帆奈、臺浩亮、太刀川彩子、田中祐壮、遠山裕佳里、長尾琢磨、長澤良佳、成澤可奈子、藤田絢花、牧田侑子、町田竜太郎、村井南、吉⽥友⾥恵
本データベースに掲載されるメラネシア民族資料は民族学考古学研究室が管理しています。研究室の活動や資料に関するお問い合わせについては研究室ホームページ(http://web.flet.keio.ac.jp/~toru38/ethnoarch/)をご参照ください。
なお、所蔵資料の基礎情報に関する調査に際して、以下の研究助成事業にご支援いただきました。
・「植民地期に収集されたオセアニア造形物に収集側と譲渡側の交錯を読み解く歴史人類学」(代表者:臺浩亮、2017年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(研究科推薦枠)、2017年4月1日~2018年3月31日)
・「20世紀初頭収集のメラネシア造形物に日本人収集者の戦略と交渉を読み解く歴史人類学」(代表者:臺浩亮、2018年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(全塾選抜枠)2018年4月1日~2019年3月31日)
・「20世紀初頭のメラネシアを巡るコレクティング・コロニアリズム研究:モノから『収集の民族誌』を描く」(代表者:臺浩亮、公益信託澁澤民族学振興基金 平成30年度 大学院生等に対する研究活動助成、2018年4月1日~2019年3月31日)
・「植民地期のニューギニアにおける『収集の現場』とモノを巡る戦略・交渉の博物館人類学」(代表者:臺浩亮、2019年度 慶應義塾博士課程学生研究支援プログラム(研究科推薦枠)、2019年4月1日~2020年3月31日)
(最終更新日 2022.1.2)