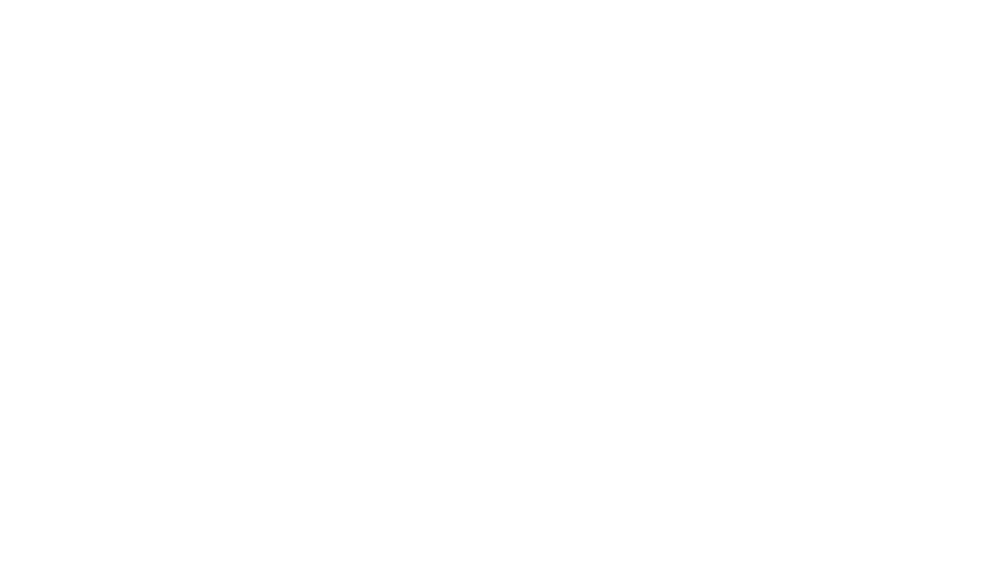
/2
草花文象嵌タイル
| 制作地 | イギリス |
|---|---|
| 時代 | 13-14世紀 |
| 技法 | 象嵌 |
| 寸法(mm) | 120×120×33 |
| 解説 | 象嵌(ぞうがん)とは、色の違うタイルピースを並べるタイル モザイクの技法が起源といわれる。赤みのある厚めの素地に掘り込みを入れ、そこへ白色の泥漿(液体状の粘土)を流し込んで模様を浮かび上がらせる。中世のフランスでも、同様の技術で修道院の床などに敷く象嵌タイルがつくられた。 |
【タイルコレクション】紀元前から近代の世界の装飾タイル
中分類: 以下の24か国を検索いただけます。(国名は地域ごと、五十音順に並んでいます)
《アジア》中国、台湾、日本、パキスタン、ベトナム
《北米》アメリカ
《中南米》メキシコ
《欧州》イギリス、イタリア、ウズベキスタン、オランダ、スペイン、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ポルトガル、ロシア
《中東》イラク、イラン、シリア、トルコ
《アフリカ》エジプト、モロッコ
※各国や地域によるタイルの特徴については、「世界のタイル博物館」のタイルコレクションをご覧ください。
【トイレコレクション】 明治から昭和にかけて日本でつくられた非水洗便器
中分類:大便器、小便器、厠下駄
※古便器の歴史や形、産地に関する解説は「古便器について」をご覧ください。
【テラコッタコレクション】 明治末から昭和初期の日本で、鉄筋コンクリート造建築を飾った陶器製の装飾材
中分類:東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、京都
※テラコッタの概要については「建築陶器のはじまり館」をご覧ください。