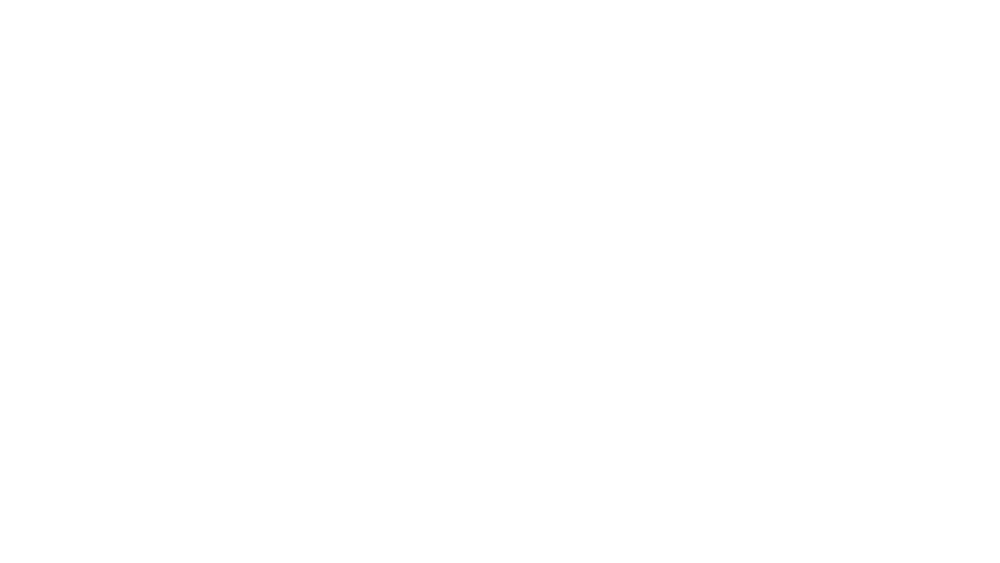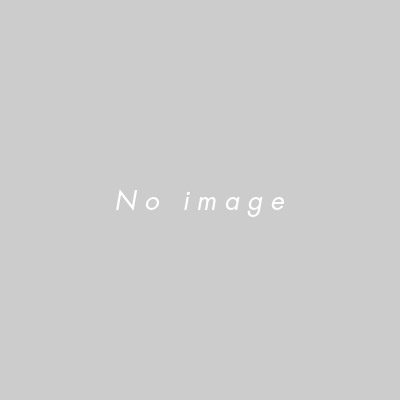懸仏
| 名称ふりがな | かけぼとけ |
|---|---|
| 大分類 | 工芸 |
| 種類補足 | 金工 |
| 員数 | 3面 |
| 材質 | 銅製 |
| 付属品 | 杉箱 |
| 法量まとめ | (1)薬師如来像懸仏 直径18.9㎝ 像高8.4㎝・(2)薬師如来像懸仏 直径17.4㎝ 像高8.2㎝・(3)千手観音像懸仏 直径12.3㎝ 像高6.5㎝ |
| 時代 | 鎌倉〜南北朝 |
| 世紀 | 14 |
| 伝来 | 熊野本宮大社伝来 |
| 解説 | 詳細な伝来は不明であるが、3点とも熊野本宮大社に伝来したと伝えられる懸仏3面である。 (1)は、円形の銅製鏡板面の外周に覆輪をめぐらし、その内側に界圏を釘で打ち付け、中央に金銅鋳造の薬師如来坐像が上下の枘で取り付けられている。透彫り光背の一部が残存し、像の左右には花瓶1対が置かれる。花瓶の挿花や像の上方の天蓋は失われている。半球状の蓮台に座る像は、頭部の鉢周りを膨らませ、体部は量感のある豊かな肉取りとする。衣紋線や台座の蓮弁の刻線には、やや簡略化がみられる。なお、左右の花形の鐶座と鐶は、それぞれ残存している。背面には、本来付けられていた檜板の繊維が観察できる。 (2)は、(1)と同様、円形の銅製鏡板面の外周に覆輪をめぐらし、その内側に界圏をもうけて外区と内区に分け、外区には飾鋲がつけられている。内区の中央には、銅製鋳造の薬師如来坐像が取り付けられている(枘穴のみ残る)。(1)と同様の造形であるが、こちらの方がやや繊細な作風となっている。像の左右には花瓶1対が置かれるが、花瓶の挿花や像の上方の天蓋は失われ、天蓋を取り付けていた釘が1本のみ残されている。鐶は失われているが、左右の獅嚙形の鐶座は残存している。背面には、基板となる檜板がほぼ全体的に残されている。 (3)は、やや小型で、外周に覆輪をめぐらし、左右の獅嚙形の鐶座が残存する。円形の銅製鏡板面の中央には、金銅鋳造の十一面千手観音坐像が取り付けられる(下の枘(丸穴)のみ残存)。銅の薄板で表現されていたと思われる千手の痕跡はみられない。像の衣紋線や台座の蓮弁の刻線は、簡略化された表現である。像の左右には、挿花が欠失した花瓶1対が置かれる(右側の上部は欠失)。 3点とも、全体的に簡略な作風ではあるが、熊野速玉大社・阿須賀神社(新宮市)や熊野那智大社(那智勝浦町)などに伝来する懸仏類と共通する特徴を持つものである。また、破損や錆化がみられるものの、檜板が一定程度残存していることから、埋納されずに伝世してきた可能性が高いものと思われる。幕末維新期の廃仏毀釈の流れの中で、熊野地域から流出した蓋然性は十分に考えられよう。 |