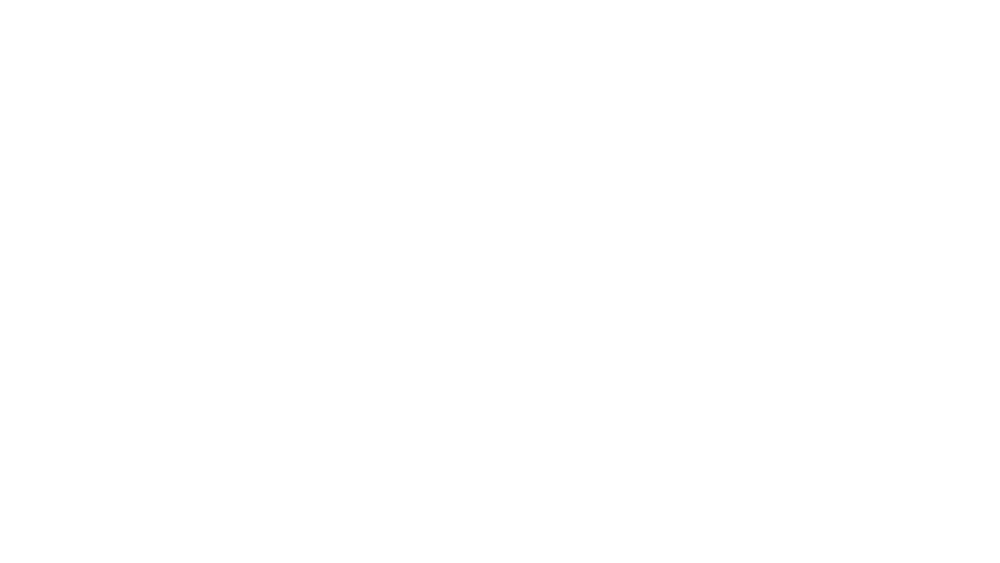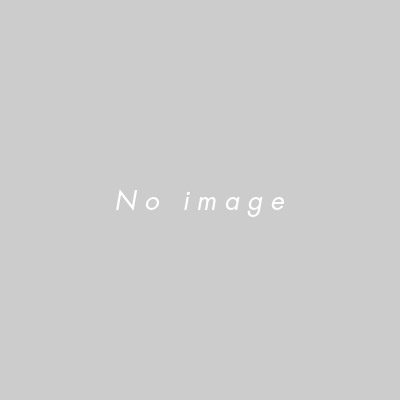頼光金時図屛風
| 名称ふりがな | らいこうきんときずびょうぶ |
|---|---|
| 大分類 | 絵画 |
| 員数 | 二曲一隻 |
| 作者 | 伝・曽我蕭白 |
| 材質 | 紙本著色 |
| 付属品 | 木箱、包裂 |
| 法量まとめ | 縦174.9 横191.0 |
| 時代 | 江戸 |
| 世紀 | 19 |
| 解説 | 江戸時代中期、京の「奇想の画人」の一人として知られる曽我蕭白(1730〜81)の作と伝えられる2曲1隻の屛風である。画題は、摂津源氏の祖・源頼光(948〜1021)が、のちに頼光四天王の一人となる坂田金時(956〜1012、幼名・金太郎)とその母の山姥に、足柄山で出会った場面を描いたものである。侍烏帽子をかぶり、鎧姿で太刀を佩いて岩に腰かけた頼光の前に、鉞を脇に置いて金太郎がひざまずき、側に母の山姥が座る情景を描く。岩から垂れ下がる植物や、深遠な岩の間を谷川が激しく流れ下る様子を背景とする。款記は、「蛇足軒曽我蕭白藤暉雄図之(花押)」と記し、「虎道」(白文方印)・「如鬼」(朱文方形内円郭印)・「蕭白」(朱文方印)の款印3顆が捺される。人物による描線の描き分けは不自然であり、雲や岩を用いた余白の広がりが間延びし、全体的に丁寧さが欠けている点など、蕭白の真筆とするには問題が多い。また、款印はいずれも微妙な点において、通例のものと差異が認められる。なお縁に貼られた小紙片によると、橋本市南部の山間部(谷奥深)の旧家に伝来した資料である。 |