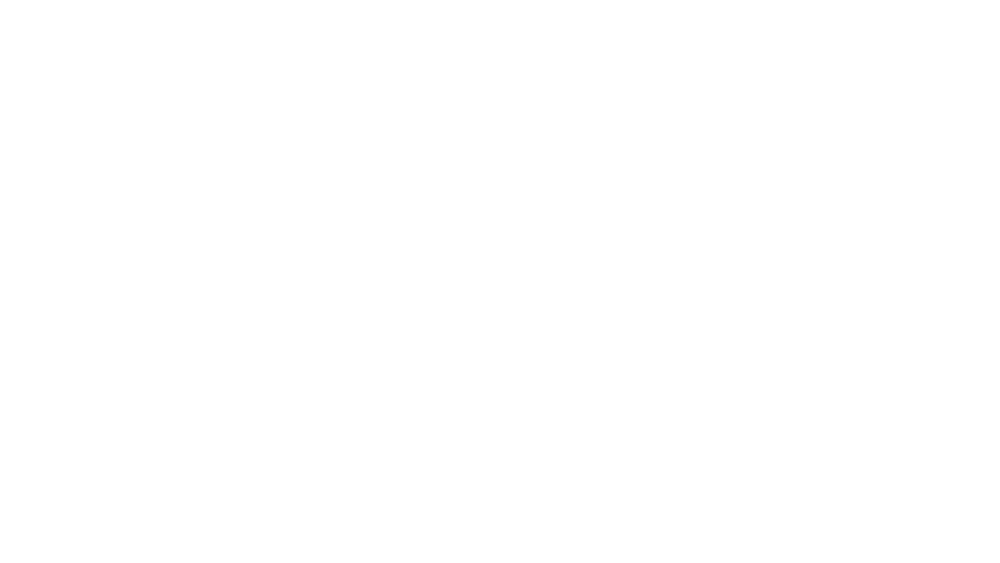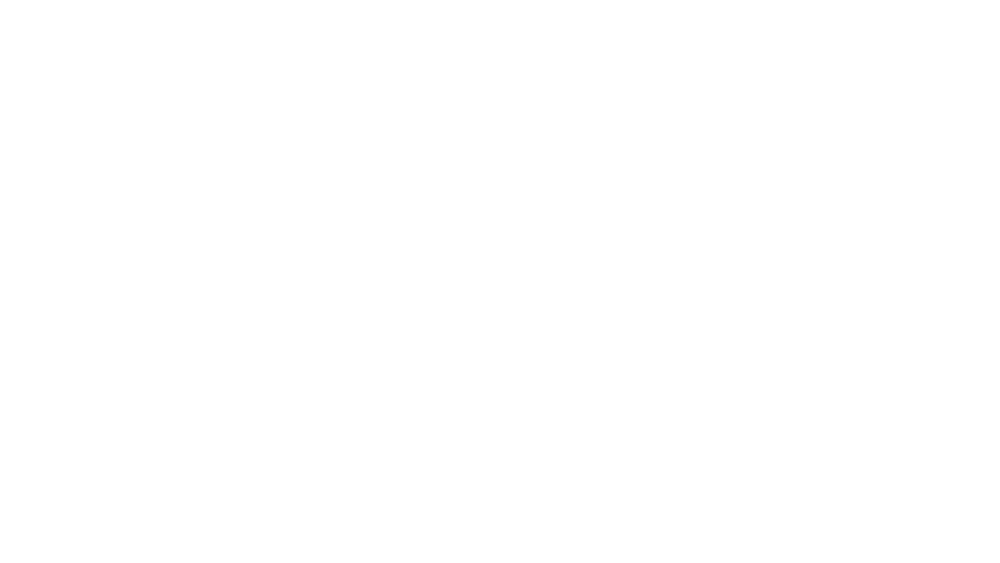刀 銘 兼元
| 資料ID | 1686 |
|---|---|
| 分野 | 美術工芸 |
| 分野補 | 刀剣・刀装具 |
| 区分 | 実物 |
| 作者 | 兼元 |
| 年代 | 室町時代 |
| 材質 | 鉄 |
| 寸法(図録用) | 刃長69.7 反り1.36 |
| 解説文又は共通解説文 | 鎬造(しのぎづくり)、庵棟(いおりむね)、中切先伸び加減でフクラ枯れる。中間反りに先反りを加え、磨り上げて踏ん張りのない姿。地鉄は小板目に板目・小杢(もく)を交(ま)じえ、やや肌立ちながら鎬地に柾(まさ)がかる。刃文(はもん)は先の尖った互の目(ぐのめ)が連れて三本杉をなす。足・葉(よう)が入り、砂流(すなが)しがかかる。地鉄が明るく白け映(うつ)りが鮮やかに現れて匂口(においぐち)も明るい。 兼元銘は大永(1521-28)~寛永(1624-44)ころまで数代にわたって同時代・同銘工がおり、本作は中でも有名な孫六(まごろく)兼元の作。 孫六兼元によって制作された刀です。 孫六兼元としては珍しく、刃文に互の目や尖り刃とともに、刃文の頭が丸く膨らんだ兼房丁子を交えています。 また本作には茎穴が4つあけられています。これは刀剣の所有者が移り変わったことに伴い、所有者に合わせてその茎側から作り変えたことによるものです。切れ味に優れた孫六兼元の刀は多様な人々に愛用されたことを示しています。(関鍛冶伝承館2024) |