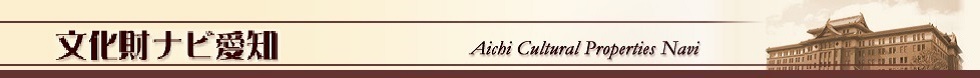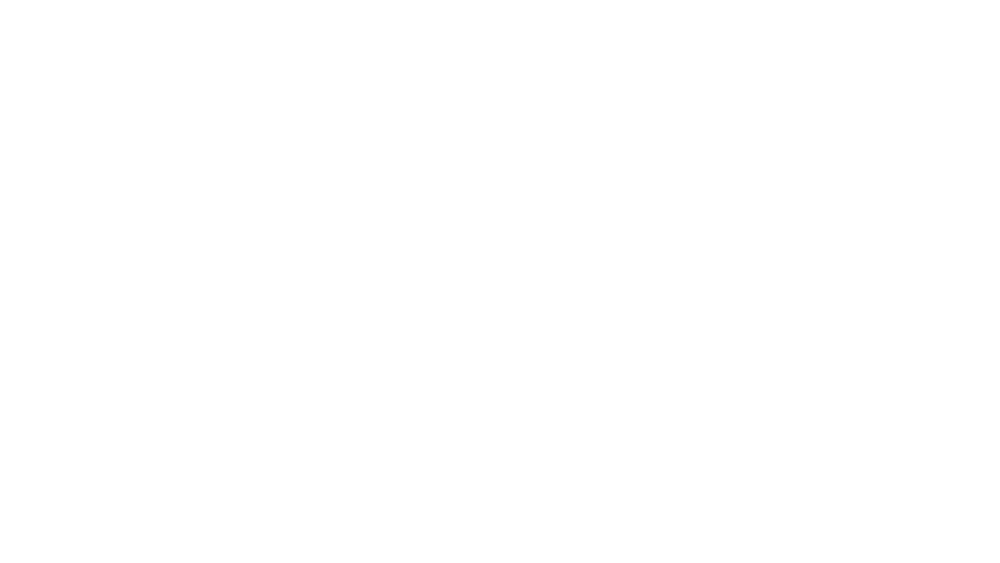旧堀田家住宅(愛知県津島市禰宜町)〈主屋 附 古図9枚/東蔵/西蔵/小蔵〉
| 分類 | 国指定 |
|---|---|
| 種別 | 建造物 |
| 所在地 | 津島市南門前町 |
| 所有者 | 津島市 |
| 指定年月日 | S53.5.31 |
| 時代 | 江戸後期 明治 |
| 詳細解説 | 堀田家は津島神社の神官に連なる家系で、初代之理(ゆきまさ)が福島正則に仕えた後、正則が広島へ国替えとなった際に帰郷し、祢宜町に家を構えたという。近世に入り酒造業、金融業や新田開発を営んで財をなし、尾張藩の寺社奉行所御用達(ごようたし)を勤め名字帯刀を許されていた。屋敷は、居室・台所・座敷を設ける主屋と、茶室、土蔵群からなる。最も古い主屋居室部は前身建物の材を用いた明和2年(1765)の建造、座敷部は明和7年(1770)の建造であることが棟札に記される。台所部は19世紀の増築という。都市計画道路拡幅のために方位を45度北に振って曳屋され、現在はほぼ北を正面としている。 主屋の居室部は、切妻造(きりづまづくり)、平入、瓦葺二階建の建物で、1階、2階ともに開口部には格子をはめ、両妻に卯建をあげる。尾張地方の町家建築の典型的な構成を示す。東側に土間を設ける片土間、2列6室を基本とする平面で、近代に一部間仕切りが変更されている。土間背面に二階建の台所部が接続し、さらに南に井戸屋形と下男の部屋が取り付く。居室部の西側に接続する座敷部は、道路から控えて建ち、前面に塀をたてて小庭を設け、西北隅には茶室、背面西南隅には湯殿・雪隠(せっちん)が取り付く。数寄屋風(すきやふう)の意匠を採り入れる座敷部の内装は明治21年(1888)の改修によるものである。茶室は両替町久田家・宗参の設計により18世紀後半に建てられたものと伝えられている。 座敷部の西には東蔵、小蔵、西蔵と呼ばれる3棟の土蔵が並ぶが、一連の庇を設けて座敷部と繋ぐ。東蔵は米穀蔵、西蔵は物置蔵で2階建、両者を繋ぐ形の小蔵は平屋建である。現状は明治24年(1891)の濃尾地震で大破したため翌年に修理したものである。 堀田家住宅は、軒の低い商家の構えを示す典型的な町家建築といえ、建造年代が確定する点で尾張地方の町家建築の時代的な指標として重要であり、その後の改造が古図との比較で確認できる点でも貴重である(溝口正人) |
はじめに
1 文化財ナビ愛知は、県内に所在する国・県指定文化財、国の登録文化財の概要を紹介するものです。
2 解説文は、指定調査の報告書等を基に、愛知県文化財保護審議会委員の監修により作成しました。
3 文化財ナビへのリンク、解説文・写真の引用等については、あらかじめ愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室にご連絡願います。
※建造物の詳細解説については、愛知県教育委員会が実施した「愛知県近代化遺産総合調査」、「近代和風建築総合調査」に携わっていただいた先生方のご協力をいただきました。なお、この調査の成果については「愛知県の近代化遺産」(平成17年刊行)、「愛知県の近代和風建築」(平成19年刊行)にまとめられています。
愛知県県民文化局文化部文化芸術課
文化財室 保護・普及グループ
Tel:052-954-6783 Fax:052-954-7479
〒4608501 名古屋市中区三の丸3-1-2
1 文化財ナビ愛知は、県内に所在する国・県指定文化財、国の登録文化財の概要を紹介するものです。
2 解説文は、指定調査の報告書等を基に、愛知県文化財保護審議会委員の監修により作成しました。
3 文化財ナビへのリンク、解説文・写真の引用等については、あらかじめ愛知県県民文化局文化部文化芸術課文化財室にご連絡願います。
※建造物の詳細解説については、愛知県教育委員会が実施した「愛知県近代化遺産総合調査」、「近代和風建築総合調査」に携わっていただいた先生方のご協力をいただきました。なお、この調査の成果については「愛知県の近代化遺産」(平成17年刊行)、「愛知県の近代和風建築」(平成19年刊行)にまとめられています。
愛知県県民文化局文化部文化芸術課
文化財室 保護・普及グループ
Tel:052-954-6783 Fax:052-954-7479
〒4608501 名古屋市中区三の丸3-1-2