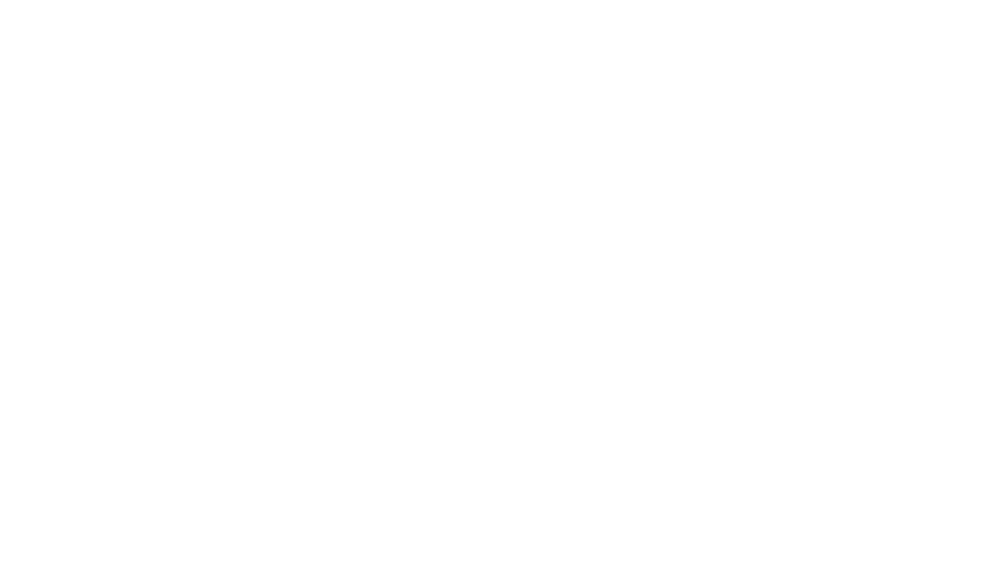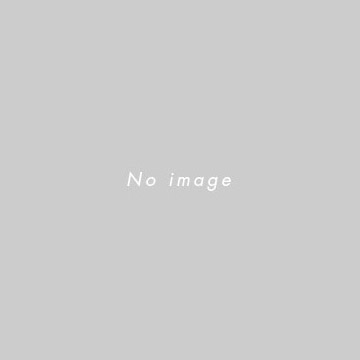【解説】平家公達草子絵巻
| 大分類 | 図書館デジタルライブラリー |
|---|---|
| 中分類 | 奈良絵本・絵巻物関係 |
| 小分類 | 平家公達草子絵巻 |
| 分野分類 CB | 歴史学 |
| 文化財分類 CB | 図書 |
| 資料形式 CB | テキストデータベース |
| +解説 | 平家公達草紙絵巻 [貴4223] 〈外題〉「平家公達草紙」(打付墨書) 〈内題〉なし 〈巻冊〉1軸 〈体裁〉巻子装 〈書写年代〉明治31年(1898〉 〈表紙寸法〉縦27.3糎×横約1033糎 〈書入・貼紙〉外題下に「己亥一月元旦写/翠谷蔵」とある。 〈奥書〉「竹内茂世先生秘蔵/明治戊戌卅一年十二月下旬写終/翠谷茂」 〈蔵書印〉「猪飼」 〈解題〉 白描絵巻。成立年・作者ともに未詳。『平家公達草紙』は、現存の『平家物語』にはないが、あたかも『平家物語』の一場面であるかのような断章の集まりの作品である。平家が栄華を極めた時代の宮廷生活の一場面が描かれている。 『平家公達草紙』には、東京国立博物館本、小川寿一旧蔵本(現早稲田大学図書館蔵)、金刀比羅本、佐藤千寿氏旧蔵本、宮内庁書陵部本が知られる。小川氏旧蔵本、金刀比羅本は東博本と同内容であるが、それ以外は重ならない。本学所蔵本は、明治31(1898)年に翠谷茂によって模写されたものである。弘化2(1845)年正月の本奥書によれば、一巻だけ伝わったものを、冷泉為(ため)恭(ちか)(1823~1864)が父の卒去以前に写したものという。為恭は、狩野永泰の子息で、家風である狩野派の絵を学び、大和絵再興に尽くした人物である。 本絵巻の内容は、東京国立博物館本と同じと思われるが、配列には違いが見られる。例えば、東京国立博物館本は邸内の中庭に公達が立つ図から始まっているが、本書では高倉院、賀茂祭見物の折の詞章から始まっている。この配列は金刀比羅本と同じであり、両者の関係の近さがうかがえる。 〈参考〉 ・桑原博史「「平家公達巻」模本について」(『ことひら』26 1971年) ・『岩波文庫 建礼門院右京大夫集付平家公達草紙』(岩波書店 1978年) ・大谷貞徳「『平家公達草紙』第二種本間の関係」(『科学研究費補助金・基盤研究(B) 「文化現象としての源平盛衰記研究」―文芸・絵画・言語・歴史を総合して―』第4集 2014年3月) |
| +登録番号(図書館資料ID) | 貴4223 |
| 所有者(所蔵者) | 國學院大學図書館 |
| コンテンツ権利区分 | CC BY-SA-ND |
| 資料ID | 143219 |
| - |